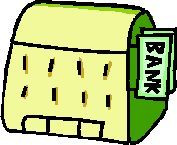
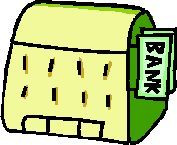
住宅ローンを組んで念願のマイホームを手に入れるとき、かならず不動産登記を行います。銀行は、住宅取得費用を貸し付ける際に、土地や建物に「抵当権」という権利を設定しますが、その抵当権が設定されていることを登記簿に載せる必要があるためです。
この「抵当権」とは、住宅ローンの場合で簡単に説明すると、何らかの理由で借主が住宅ローンを払えなくなってしまった場合、銀行が裁判所を通じて抵当権の登記のある土地や建物を売却し、そのお金で住宅ローンを回収することができる権利です。
住宅ローンは消費者を対象としたローンのなかでも、最も貸し付け金額が大きく(数百万円から数千万円)、返済期間も長期(25年や35年など)にわたります。
そのため、銀行としては、抵当権を設定し、登記することで、貸し倒れリスクを回避する必要があり、そのため住宅ローンと登記はセットになっています。
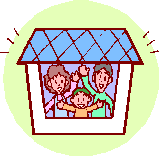
住宅ローンを組むときに必要な登記申請は、どのようなものがあるのでしょうか? 住宅ローンに対する抵当権の登記申請だけでしょうか?
また、登録免許税はいくらでしょうか?
住宅ローンの抵当権を登記申請する場合、他にも関連する登記申請を行う必要があります。この組み合わせは、住宅の取得方法により、様々な組み合わせがあり、なかなか購入者の方には分かりにくい部分でもあります。
基本的な考え方は、①所有者はだれか? ②所有者の住所はどこか? ③借入は何口か? によりますが、代表的なケースごとに必要な登記を説明します。
A)新築分譲住宅(土地・建物)、中古住宅(土地、建物)、中古マンション(土地持分、建物)購入の場合
①所有権移転登記(買主へ所有権が移転したことを登記する。)
②抵当権設定登記(買主が住宅ローンを組んでいるので、その住宅ローンの抵当権設定登記を行う。)
B)先に土地を買い(土地購入ローンあり)、注文住宅を新築した場合
まず、建物表題登記を行う(土地家屋調査士が、建物の現場確認、測量、調査を行い、登記簿の建物データ部分を登記します。)
①土地所有者住所変更登記(土地を買った際には、別の住所であったので、新築建物の場所に住所を変更する登記。)
②土地抵当権の債務者住所変更登記(土地を買った際には、別の住所で債務者として登記してあったので、新築建物の場所に債務者の住所を変更する登記。
③建物所有権保存登記(新築建物の所有権者は誰かを登記する。)
④抵当権設定登記(追加)(土地購入時のローンの抵当権を建物に設定する登記。)
⑤抵当権設定登記(建物新築代金のローンの抵当権を土地と建物に設定する登記。)
C)建替えの場合(仮住まいに住民票を移さなかった場合)
まず、建物表題登記を行う(土地家屋調査士が、建物の現場確認、測量、調査を行い、登記簿の建物データ部分を登記します。)
①建物所有権保存登記(新築建物の所有権者は誰かを登記する。)
②抵当権設定登記(建物新築代金のローンの抵当権を土地と建物に設定する登記。)
D)住宅ローン借り換えの場合(登記簿の所有者住所が現在の住民票と同じ場合)
①抵当権設定登記(借り換え後の新規住宅ローンの抵当権設定)
②抵当権抹消登記(借り換え前の旧住宅ローンの抵当権抹消登記)


登記費用には、①登録免許税(税金の一種で、誰が登記申請を行っても必要な法定費用)②司法書士費用(登記代理人を仕事として行うことのできる国家資格者の報酬)の2種類にわかれます。
不動産登記は、本来、申請人自ら行うことができる制度ですが、住宅ローンを組む場合、お金を貸す銀行とお金を借りる消費者の双方から委任を受けた司法書士が登記申請代理人として申請を行います。
これは、住宅ローンを融資する場合、融資実行日(実際に住宅ローンの借入金が借主口座に振り込まれ、不動産の売主や建築会社に支払を行う日)に確実に登記申請が提出され、なおかつ、提出された登記申請が後日、間違いなく完了することが求められるからです。
万が一、融資実行日に登記申請がなされなかったり、登記申請がなされたとしても、その登記申請が却下されてしまうと、住宅ローンを融資した金融機関は損害を被る恐れがあるため、銀行などでは、必ず司法書士に登記申請を依頼します。
それぞれの銀行には、お抱えの司法書士が存在しますが、借主指定の司法書士に登記申請を依頼してもよい、とする銀行も多くあります。司法書士報酬は、各事務所によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。
ここでは、このうち、登録免許税について、ご説明します。
登録免許税には大きく分けて以下の区分があります。
①定額課税・・・土地や建物の数に対して、一律に課税する方法。例えば、上記B)の①②、D)の②などで、不動産の数かける1000円
②定率課税・・・土地や建物の評価額などや、住宅ローンの借入額(抵当権設定額)などの金額に対して、「何パーセント」という形で産出する方法。例えば上記A)①=土地や建物の固定資産税評価額×1% ②=住宅ローンの借入額×0.4%、B)の③=建物の登記床面積×約7万円(法務局や市町村によって異なる)×0.4%など
ちなみに上記B)の登記申請の場合で、土地1筆・建物1棟・建物登記床面積185㎡・土地のローン1500万円・建物のローン1000万円の場合で登録免許税を計算すると、以下のとおりになります。
①土地所有者住所変更登記=1000円
②土地抵当権債務者住所変更登記=1000円
③建物所有権保存登記=185㎡×70000円×0.4%(減税証明を使うと0.15%)=51800円(減税証明使用19400円)
④抵当権設定登記(土地ローンの建物追加)=1500円
⑤抵当権設定(建物ローンの新規設定)=1000万円×0.4%(減税証明書を使うと0.1%)=40000円(減税証明使用10000円)
なお、この場合の当事務所の司法書士報酬基本額は、以下のとおりです(消費税含まず、附帯報酬(減税証明書取得や登記簿謄本、住民票取得など)含まず、の参考価格)
①7000円から9000円
②7000円から9000円
③12000円から16000円
④26000円から29000円
⑤21000円から23000円