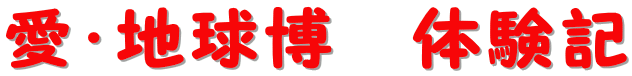
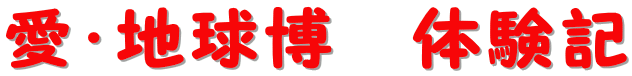
![]()
| 瀬戸会場パビリオン所在地 |
 |
| <市民パビリオン・海上広場> Civic Pavilion & Kaisho Plaza
協賛・協力: トヨタ自動車 名鉄グループ フジキン 東新住建 ファミリーマート 大塚製薬 ナナオ みずほ証券 バッファロー 産業技術総合研究所 プラスビジョン ベネッセコーポレーション ウェブソーシング HP: http://www.expo-people.jp/ <コンセプト> あなたの「地球の愛しかた」見つけてください 日本全国から、世界から市民参加のプロジェクトが大集結!毎日入れ替わりでさまざまなイベントを開催します。特別な知識なんて必要ありません。大切なことは“集まること”、そして“参加”すること。あなたの「地球の愛しかた」きっと見つかるはずです。 <構成> 対話劇場(市民パビリオン) 「グローバルダイアローグ」をテーマに、環境問題をはじめ平和、福祉、文化、健康など、地球に生きる私たちが抱えるさまざまな問題に対して、多様なミッションを持った市民やNPO/NGO、個人が、トークイベントやディスカッション、コンサートなどを展開します。最先端技術を駆使したアクセスグリッドによる世界各地をリアルタイムに結んだ議論や、海外、国内から著名人をゲストに招いたフォーラムなど、画期的な対話がおこなわれます。 対話ギャラリー(市民パビリオン) テーマは「地球の希望」。個人をはじめ、NPO/NGOが地球に「希望」を与える姿を、展示とワークショップで伝えます。同時代に生き、地球のために考え、活動する人々と出会いに来てください。また、リアルタイムな地球を体感できる「触れる地球」や市民の生の声が聞ける「地球の授業」も随時開催します。 ・地球回廊 「地球の窓」世界の多地点とリアルタイムでコミュニケーションします。 「触れる地球」生きた地球環境の動態を可視化するマルチメディア地球儀です。 海上広場 森に囲まれた瀬戸会場の中央に位置する海上広場では「地球市民大交流祭」が繰り広げられます。身体と感性を使って、地球のこと、世界のことが学べるワークショップやパフォーマンス、コンサートなどがおこなわれます。つくったり、遊んだり、奏でたり、踊ったり…、子どもからシニアまで、一緒になって体験できる野外空間です。 <開館時間> 4月26日〜7月19日 9:00〜18:00 7月20日〜8月31日 9:00〜19:00 9月 1日〜9月25日 9:00〜18:00 <観覧所要時間> 約30〜60分(展示内容により異なります)
このページTOPへ |
||||
| <ウェルカムハウス> Welcome House
HP: 愛・地球博 市民放送局 http://www.expo-civic-tv.jp/ <コンセプト> ウェルカムハウス 瀬戸会場の玄関口として、愛・地球博のスタートラインとなった「海上の森」について学べます。また、市民による「愛・地球博 市民放送局」が開局。愛・地球博の市民レポーターとなって、21世紀はじめての万博を報道してみませんか。 <開館時間> 4月26日〜7月19日 9:00〜18:00 7月20日〜8月31日 9:00〜19:00 9月 1日〜9月25日 9:00〜18:00
このページTOPへ |
||||
| <瀬戸愛知県館> Aichi Pavilion Seto
出展: 愛知県 HP: http://www.aichiken-kan.jp <コンセプト> 「森の鼓動と呼吸」〜かつてない自然発見の場〜 瀬戸愛知県館は、今回の国際博覧会の会場づくりを巡ってさまざまな議論がなされた「海上の森」の一隅にあります。このパビリオンは、万博後には「海上の森」の自然を学び育むための拠点とすることを前提に計画しました。パビリオンでは日頃見過ごしてきた多様な生命世界をダイナミックに実感できます。愛知県民による地域に根ざしたエコ活動の出展では、来館者の参加もお待ちしています。 <構成> ライブラリー空間 愛知県内で絶滅が危惧されている生物の姿、昔の人々の生物との係わり、瀬戸愛知県館のエコ対応工事などを書斎風の空間で紹介。 ギャラリー空間 「森の劇場」 海上の森の四季の表情、そしてさまざまな生物の姿を2年間にわたって記録し続けた迫力ある特殊映像と世界初の7+1サラウンドシステムで体感するシアター。館内に移植したコナラの木の物語も込めて、この森を残すことができた気持ちを伝える。上映内容は「虫の目」と「森の一瞬」の2種類あり、上映時間はともに約15分。 森の回廊 移植したコナラが見守る吹抜け空間に、愛知県内465校、約1万人の子どもたちがリサイクル素材などで身近な昆虫などを工作し、ハチの巣をイメージした六角形のケースに納められた作品を展示。「鼓動・呼吸する繭」の内部には、「レッドデーターブックあいち」に記載されている3種の絶滅種、ニホンオオカミ、ニホンアシカ、ニホンカワウソのタイプ標本(生物の学名がつけられた時のオリジナル標本)を特別展示。 コラボレーション空間 「にぎわいの里」 自然と共生する社会づくり「エコ・コミュニティ活動」に取り組む県民が主役とするコーナー。さまざまな活動の姿を、わかりやすく親しみやすい展示・催事で紹介。 ◆愛知グリーンマップ2005=地域のグリーンマップ展示◆あいち環境絵本=公募絵本作品の展示・童美連協力作品の展示◆愛知自然と暮らしの暦=公募CDアート作品の展示◆愛知エコ・コミュニティ活動紹介=公募団体の活動内容発表◆エコの知恵袋=公募アイデアを館内運営業務で実施紹介 <環境への取り組み> コナラの木 瀬戸会場周辺工事で伐採予定だった高さ約20mのコナラの木を、建物の中心、吹抜け空間に移植。 自然にやさしいメシュカゴ 自然の傾斜地は、石積みメシュカゴを段上に並べることで安定化を図る。メシュカゴ内部は水や空気が通り、生物が棲息できる。 アテンダントユニフォーム 愛知県館アテンダント、クルーのユニフォームは、竹のスジスジ部分の繊維を取り出して糸をつくり、合服がウールと夏服がコットンと合わせた生地で縫製。 森を守る工夫 博覧会終了後は仮設部分を撤去し、恒久部分は「里山学びと交流の森」の拠点施設として整備。仮設部分の外壁や床に使用する木材は、下山村の新設小学校で再利用される。 <開館時間> 4月26日〜7月19日 9:00〜17:30 7月20日〜8月31日 9:00〜18:00 9月 1日〜9月25日 9:00〜17:30 <観覧所要時間> 約60分 長久手愛知県館へ
このページTOPへ |
||||
|
<瀬戸日本館>
Seto Nippon−Kan
出展: 日本国政府(経済産業省) HP: サイバー日本館 http://www.nippon-kan.jp/ <コンセプト> 「つなぎ直そう。人と自然」 テーマは、「自然と生きる日本人の知恵・技・こころ〜自然とつながる感性を取り戻そう」。 日本人には、自然と折り合う生活に心の豊かさを感じとる力があります。それは、古くから育んできた「知恵・技・こころ」。災害の防止、快適な生活、資源の有効利用など科学や技術のみでは解決出来ない問題への解決の糸口を提示します。アーティストたちのパフォーマンスがあなたの想像力を揺さぶり、自然とのつながりを実感しながら懐かしい記憶を呼び戻してください。 <構成> プロローグ 和紙を使用した壁面、床に広がるLED照明の紋様、光・音の演出など複合的な構成により、現代的な工夫を施した奥行きのある映像を四方に展開。窓から四季折々の美しさを眺め、日本人の「知恵・技・こころ」に包み込まれる、日本人独特の感性を展示空間全体で美しく表現。 群読 叙事詩劇 「一粒の種〜響きあう知恵の記憶、わたしがはじまる。」 中央ステージを囲むように観客席が配置され、さらにその周りを多数の演者が囲む劇的空間。日本人が古くから持つわらべ歌や祭りの掛け声を台詞にし、集団で語る「群読」という演劇手法で叙事詩劇を演出。15分間という凝縮された時間の中で30名以上の出演者の語る声や日本を代表する演劇スタッフが、瀬戸日本館に集結。万博では初の試みとして、1日約20回、会期中185日毎日、「群読 叙事詩劇」の舞台を公演。 アートギャラリー 「光と風の庭」 2人の美術家で構成されるアート空間。「知恵」・「技」の歴史とともに新しい自然とのつながりを表現している。 <環境への取り組み> 風の塔(ソーラーチムニー)と地中熱利用による自然通風 外の冷気を取り入れ内部へ通す、空気流動スペースを確保し、その空気を抜くために、2階展示室上にはソーラーチムニー、最上部には自然換気窓(スウィング窓)を設置。自然風力によって開閉することにより、風の道を作り出し、暖まった空気が常に外部へ流れ、新しい冷気を常に取り入れることで、機械に頼らない自然換気を促進。さらに2階展示室には、新鮮な外気を地中約4.5mに打ち込んだ12本の二重パイプを通じて冷やしてから供給。 環境に配慮した外壁木質パネル 自然環境にやさしい、有機材の木質パネルを外壁に使用。加工が簡単で、会期終了後には資材再利用することにも配慮。 ヤシ殻マットと在来種による屋根緑化システム 4階の屋根は防水処理を施した金属成型板の上に、ヤシ殻マットを置いた屋根緑化工法を採用。ヤシ殻マット屋根緑化は、建物の熱負荷を低減すると同時に、周辺の景観に溶け込むことで環境との調和を図っている。また、ヤシ殻マット緑化システムは、そのまま他へ運ぶことが可能であり、会期終了後のリユースにも配慮したシステムとなっている。 <開館時間> 4月26日〜7月19日 9:00〜17:30 7月20日〜8月31日 9:00〜18:00 9月 1日〜9月25日 9:00〜17:30 <観覧所要時間> 約40分 長久手日本館へ
このページTOPへ |
||||
| <里のビジターセンター> <里の自然学校>里山遊歩ゾーン Village Visitor Center Village Nature School − Satoyama Trail Zone
HP: http://www.jeef.or.jp/expo-nature-school/ <コンセプト> 自然そのものがパビリオン 愛・地球博の会場は、面積の約半分を自然のままに残しています。そして、里の自然学校は、まさにその残された自然のゾーンが舞台。インタープリターと一緒に自然の中に出かけ、自然のもつ素晴らしい仕組みや命の力を学ぼうという愛・地球博のメインテーマ「自然の叡智」を、まさに「体感」できるのが、この「里の自然学校」です。 <構成> 自然体感プログラム 里の自然学校では、さまざまな自然体感プログラムを提供します。自然体感プログラムは、森の中での“いろんな時間”を演出。来場者を自然の中へと案内するスタッフ、インタープリターと一緒で楽しい時間、森の中でほっとする癒しの時間、発見と気づきの時間、五感の全てをとぎすます時間。これらを通して、これからの人と自然とのおつきあいを考えるプログラムです。インタープリターが、自然の中にあるもの、自分の体や声、ポケットに詰め込んだ小道具などを使って、森の中での楽しいひと時を演出します <開館時間> ビジターセンター 9:30〜17:00 プログラム受付 10:00〜16:55 <観覧所要時間> 約40〜75分(プログラムにより異なります)
このページTOPへ |
画像・文章等の無断転載厳禁。
© AICHI-univ.Night-GolfClub 2005.
Photo:© AICHI-univ.Night-GolfClub 2005.